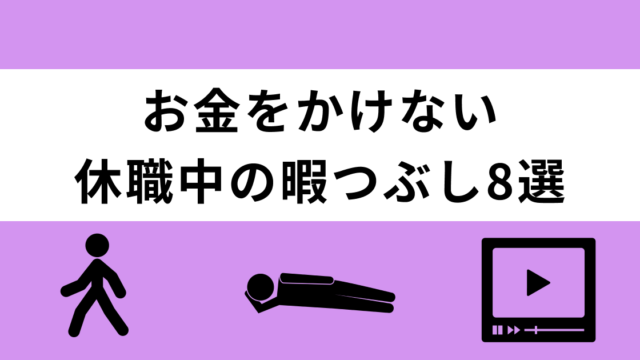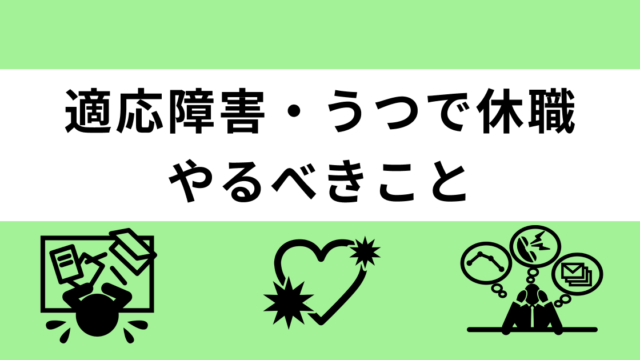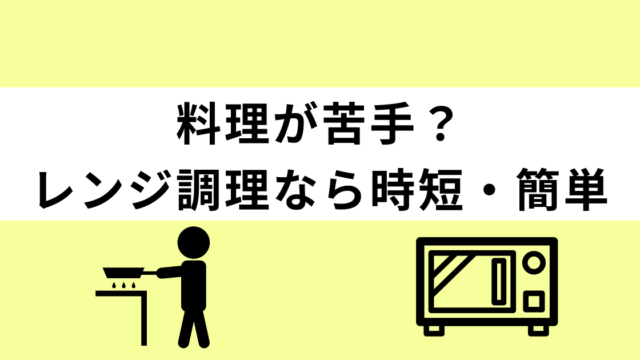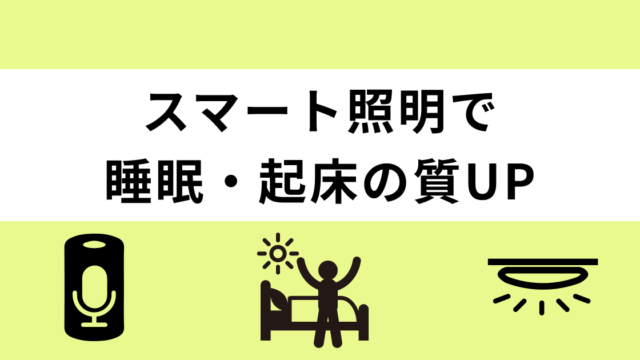毎朝起きる時間なのに、すんなりと起きれない。
起きれたとしても、すっきりと起きることができない。
今回はそんな朝が苦手な人のために、同じく朝が苦手な自分がやっている、不快感なく目覚めて、起きるためにやっている8つの工夫を紹介いたします。
起床するたびに「まだ眠い」「もう少し寝たい」思いとずっと戦いながら考えた、起きられない3つの大きな要因と、それに対する具体的な対応策をまとめました。
「寝るとき」「目覚めるとき」「起き上がるとき」に原因
そもそもなぜ、朝すぐに起きられないのでしょうか。
朝起きるまでの3つの段階、寝るとき、目覚めるとき、起き上がるときに起きられない原因があります。
詳しく説明していきます。
睡眠の量や質の不足
寝るときの問題とは、睡眠の量が足りていないことや寝る前までの生活による睡眠への悪影響です。
自分に必要な睡眠時間や良い睡眠を取らないと、目覚めたときにもう少し寝たいと思ってしまう寝足りない感覚になり、すんなりと起きられません。
その状態にも関わらず仕事や用事で時間が差し迫り起きざるを得ないのでは、求めている睡眠量を取れていないことに身体が不快感を覚え、すっきりとした目覚めになりません。
不快な目覚めを避ける
不快な要素は、目覚めるときにもあります。
例えば目覚まし時計の大きな音は、静かな環境にある身体をびっくりさせることで起こしているため、良い目覚めにはなりづらいです。
目覚めたときの気分が悪いと、起きるアクションを取るためのエネルギーが出てきません。
身体にとってもっと自然で、不快感の少ない方法を使って目覚める方法に工夫するべきです。
起き上がりたい気持ちになれるか
そして人は目が覚めただけでは起きたといえず、起きあがって活動できる状態になってこそ起きたといえます。
目が覚めた、目を開けただけではまだ布団の中にいますから、どう起き上がって布団から出るのかが起きれない人に立ちはだかる障害です。
朝起きられない人は布団の中にいたい気持ちの方が、布団から起き上がろうとする気持ちよりも大きいので、起き上がりたくなる工夫をしなければなりません。
これら3つの問題を克服するために、自分が実際にどんな方法を取っているのかをご紹介します。
寝るときは自分にあった睡眠時間を確保する
まず寝るときに心がけている2つの工夫は、以下のとおりです。
- 身体が必要としているたくさんの睡眠をとる
- 睡眠時間と質を確保するために、就寝前は電子機器を遠ざける
順番に解説していきます。
必要なだけ睡眠時間を取れば自然と起きられる
起きるためにまずやらなければならないことは、身体が求めている睡眠時間を確保してその分しっかりと眠ることです。
十分な睡眠を取れていないにも関わらず起きようとするのは、身体に無理を強いているのでスムーズな目覚めには繋がりません。
朝起きづらかった頃の自分を振り返ると、6時間半から7時間くらいの睡眠しか取れていませんでしたし、繁忙期の仕事によってさらに短くなると「まだ寝ていたい」と起きた瞬間に思います。
しかし8時間を基準に睡眠をとるようにしてからは、目覚めたときの寝不足の感覚がなくなりました。
必要な分の睡眠を取ったから起きよう、と身体が判断しているのです。
自分が経験した変化から気づいたのは、必要な睡眠時間が足りないと、もう少し寝たい、寝不足の信号を目覚めたときに身体が発することです。
そういった感覚に反して仕事や予定があるからと無理やり意思の力で起きると、まだ寝たいと思っている身体との不和で不快感につながります。
それは睡眠による十分な休息が取れていない身体を、強制的に動かしている状態にほかなりません。
眠りが足りない身体と、起きなければと思う意思の不和を解消して起きやすくするためには、どれだけ意思の力を強くするかではなく、どれだけ身体が必要としている睡眠を確保できるかこそが大事です。
必要な睡眠を取ることができれば、自然に身体は目覚めます。
意思の力を使って無理やり起きる方法は長続きしませんし、できているとしても思考能力が鈍ったり判断力が落ちたりと生活に影響が出ます。
スムーズに朝起床し、その後活動していくためにも、必要な睡眠時間を確保しましょう。
最適な睡眠時間を知るために、自分で実験する
自分に必要な睡眠時間は、自分の感覚をもとにして決めるのが最も良い方法です。
ショートスリーパー、ロングスリーパーという言葉が存在するように、人によってどの程度の睡眠時間を必要とするかは変わります。
年齢を重ねるに連れて睡眠時間が短くなったり、季節によって変化したりすることも研究によって明らかになっています。
したがってどの程度の時間睡眠を取れば良いのかは、自分自身で確かめる必要があるのです。
では自然に目覚めるための睡眠時間を知るには、どんな方法を取ればよいでしょうか。
実際にやってみて効果的だったのは、数週間のあいだ眠くなったときに布団に入り、目覚ましをかけずに自然に起きるまでの時間を計る方法です。
何時に寝なければならない、起きなければならない縛りをなくし、自然な状態の身体に寝起きする時間を任せることで自分にあった睡眠を身体自身に導き出してもらいます。
しかし毎朝決まった時間に出社しなければならない社会人には、自然な寝起きに任せて生活を送るのは難しいでしょう。
目覚ましをかけなかったために朝起きられず遅刻してしまったり、また飲み会や残業があると十分な睡眠時間を確保できなかったりします。
自分自身もこの方法を試したのは、長い間に渡って仕事や急ぎの用事もなかった休職期間でした。
代わりの方法として、普段よりもある程度長い睡眠時間を取ると決め、一定期間それを続けることのも考えられます。
起きたときの感覚によって、さらに睡眠時間が必要なのか、多少短くしても良いのかを調整するとよいでしょう。
いずれの方法をとるにせよ注意しておきたいのは、始めたばかりの数日は睡眠時間や感覚が参考にならない助走期間となることです。
睡眠を満足に取れていない状態から始めるため、最初は睡眠時間を取り戻そうと必要以上に睡眠を長く取ってしまう傾向があります。
平日忙しく働いて満足に寝られていない人が、休日になるとお昼まで寝ているのと同じことが起こっているのです。
寝る時間を確保するため、PC・スマホは就寝1時間前からは触らない
就寝1時間前までにPC・スマートフォンの使用をやめてブルーライトを浴びないようにすると、布団に入ってからの寝付きがよくなります。
スマホやPCが発するブルーライトを浴びると、セロトニンと呼ばれるホルモンが分泌されます。
セロトニンには脳を覚醒させたり、脳を朝だと感じさせて体内リズムを調整する効用があるため、夜にブルーライトを浴びてセロトニンが分泌されると寝付きが悪く睡眠の質も低下してしまいます。
そのため就寝1時間前からは電子機器の使用を制限しブルーライトを浴びないようにすることで、身体を夜だと認識させて眠るモードへと切り替えさせましょう。
就寝直前までスマホやPCを触っていたときの自分は布団に潜ってから寝るまでに30分ほどかかっていましたが、1時間前に使うのをやめてからは10分くらいで寝付けるようになり、その分眠れる時間も増えました。
寝るまでのスマホ・PCを触れない時間は、歯磨き・ストレッチ・瞑想のような心身をメンテナンスする時間に当てたり、読書・ブログ・次の日の予定整理など電子機器から離れることで深く考えられることに費やしています。
目覚めるときは不快感をなくす工夫をする
次に、目覚めるときにしている工夫はこの3つです。
- 不快な刺激の目覚まし時計は使わない
- スマートライトで、起床にあわせた光の刺激を受ける
- スマートバンド・スマートウオッチで、振動の刺激で目覚める
なるべく目覚ましは使わない
目覚まし時計は大きな音をだすことで意識を目覚めさせる一方、身体にとっては不快な刺激にほかなりません。
朝の静かな環境でいきなり目覚まし時計の音が鳴り響くと、身体はそれに反応して驚き、血圧や心拍数が一気に上昇する緊張状態となります。
もっと優しく自然に目覚められたほうが、目覚まし時計を使って毎朝びっくりして起こされてるよりも気分がいいです。
起きている状態でも耳元で大声を出されたら良い気分になんてならないのに、リラックスして寝ているところでされたら更に気分が悪くなります。
そのために、できる限り目覚まし時計の音や聴覚に頼らない目覚め方を工夫します。
スマートライトを使って、光の刺激で目覚める
朝目覚める時に、最も身体にとって自然な刺激は光です。
起きる時間に合わせて光をコントロールすれば、すっきりと目覚めることができます。
ヒトは元来電気がなかった時代には太陽の出入りによって1日の始まりと終わりを決めていましたから、光によって目覚めをコントロールする方法はヒトにとって最も自然です。
そこでスマートライト(スマート電球)を使えば、朝起きる時間に合わせて部屋を明るくすることによって、光を浴びることができます。
目覚まし時計のように時間を予め設定しておくことでスマートライトを自動的に点灯させる事ができるため、起きたい時間に合わせておけば明るさで目覚められます。
シーリングライトか、電球タイプかはお部屋に合わせて選択すると良いでしょう。
目をつぶっていても、アイマスクをしていても周囲が明るくなっているのは感じられますから、スマートライトの点灯に合わせて起床できるように設定してしましょう。
太陽が昇るように少しずつ時間をずらして明るさを上げるのも、快適な目覚めにする上では効果的と言われています。
スマートライトではなく更に強い光を発する光目覚ましも近年は注目されていますが、目覚まし時計としてはかなり値が張ります。
目覚まし時計にそれほどの金額は出せなかったので、もっと気軽に導入できて通常の室内照明としても使えるスマートライトを代わりに使っています。
スマートバンドを使って、刺激が少ない振動で目覚める
照明の光による刺激と併せて、バイブレーション機能があるスマートバンド・スマートウォッチを使うことで身体に直接的な振動を与えるのも効果的です。
スマートバンド・ウォッチで設定できる振動は強くなく、音よりも刺激が小さいため、単体で使うと気づかず目覚められないことがあります。
そのため振動を光と一緒に使うことによって複数の刺激を与えるようにすれば、音よりも不快感なく目覚められます。
光はゆっくりと目覚めを促すタイプの刺激なため、設定した時間に目覚めるにはアラームでセットされた振動を使うと「光によってぼんやり目覚める→振動によってはっきりと目覚める」と段階を踏んで起床できるのです。
スマートバンド、スマートウォッチであればアラーム機能はたいてい標準でついており、自分が使っているのはコスパを優先したXiaomiのmi smart band6です。
mi smart band 6 を振動による目覚ましに使うにはスヌーズ機能の無い点が不満ですが、複数個のアラームを設定することで代用しています。
起き上がるときは身体と心を前へと向かわせる工夫をする
そして起き上がるときはこのようなことを心がけています。
- 身体を自然に起こせるよう、目覚まし時計の置き場所を工夫
- 目覚めを良くする太陽の光を浴びれるような位置で寝る
- 起きたあとのちょっとした楽しみを用意しておく
目覚まし時計を足元に置き、身体を起き上がらせる
目覚まし時計を足元に置くことで、止めるためには上半身を起こして腕を伸ばす必要があるため、その過程で身体を起こしています。
寝ている体勢から抜け出すために意思の力で起き上がろうとするのではなく、無意識でやらせるための工夫です。
目覚まし時計は音が不快なためできるだけ使いたくありませんが、一番確実に起きる手段であることも確かなので、光や振動でも起きなかったときに鳴るようにしています。
不快な音が鳴る前に目覚め、すかさず時計が鳴るのを防ぐために身体を起こす流れによって、布団から出るための体勢に自然に移行します。
目が覚めていても寝ころがったままでいるとそのまま二度寝しかねませんし、それを防ぐためには布団から出ずとも上半身だけでも起こしておくのが肝心です。
窓際で寝て、起きたら太陽の光をすぐに浴びる
目覚めをはっきりとさせて生活リズムを整えるのに、陽の光を浴びるのは効果的です。
そのためカーテンに手が届くような窓際の位置で寝れば、目覚めたときにカーテンを開けて寝ながらでも光を浴びられます。
太陽の光を浴びると「PC・スマホを就寝1時間前からは触らない」でも説明したセロトニンが脳内で分泌されます。
セロトニンには脳を覚醒させる作用があるため夜は避けたほうが良いですが、朝は積極的に分泌すれば生活リズムを整えたり目覚めをはっきりさせる助けとなったりするのです。
わざわざカーテンを開けるために布団から起きて窓へいく、なんてことはできないので寝転がった状態でもカーテンを開けられるよう、カーテンが手で届く位置で寝ましょう。
こうすることで寝転がっていてもカーテンを開けて陽の光を浴びることができ、次第に目覚めがはっきりして起き上がる意思がついてきます。
起きた後のご褒美を用意して、起き上がるやる気を出させる
必要な睡眠時間を取り、意識がはっきりするくらい目覚めたとしても、布団から出ようと気持ちが前向きになるかどうかは別です。
行きたくない仕事や面倒な用事が待っていることが頭をよぎると起き上がる気も失せ、時間が迫っているから渋々起きたとしても気分が良くなることはないでしょう。
仕事や用事をなくすことはできませんが、それに取り掛かるよりも前に「布団から起きたらこれがある」「布団から出たらこれをやっていい」ご褒美を用意して、とにかく布団から出る意思を持たせることはできます。
手軽に用意できてすぐに嬉しい気分にもなれるのでおすすめなのが食べ物や飲み物です。
目に見える所にあれば翌朝思い出してテンションが上がりますし、口に入れれば「美味しい」という気持ちになる即効性もあります。
自分の場合はお湯で溶くタイプのミルクココアを用意して、毎朝「起きたら飲める」と思って起き上がっています。
食べ物飲み物よりも効果は薄れるものの、youtubeや録画しておいたテレビ番組のような目に見えづらい楽しみでも構いません。
起き上がったあとに嬉しくなれるモノ・コトを用意しておいて、布団から抜けるための口実をつくりましょう。
どこに問題があるのかを見極める
寝るときは、自分に必要な睡眠時間をとる。
目覚めるときは、なるべく心地よい刺激で。
起き上がるときは、気持ちを前向きにする要素を用意する。
朝が苦手だという人は、振り返ったときに3つのうちどこかで、あるいは全てでつまづいています。
ご紹介した9つの具体例を参考にしていただき、ひとつひとつ原因を取り除いたり、対策を立てたりしましょう。